
蓄音機の演奏会を東京都内で定期的に開催し、その魅力を多くの人に伝えている「オヤビン佐藤」こと佐藤隆俊さん。1930年代にイギリス・グラモフォン社(ビクター)で製造されたポータブル蓄音機HMV102を所持し、集めたSPレコードは約3000枚! カメラマンとして活躍する傍ら、NPO法人シブヤ大学授業コーディネーター、東京にしがわ大学スタッフの顔も。「自分がおもしろいと思ったものは誰かもおもしろいと思うはず」という想いが活動の原点になっているといいます。
|至極の一言|
おもしろいと思っていること、ハマっていることを人に話すことで、自分が違うところに連れて行ってもらえるんですよ。
趣味が高じて、蓄音機の魅力を伝える側に……
崎谷:そもそも蓄音機とは、どういうものですか? 手動なんですよね?
佐藤:そうです。ゼンマイの力で回しているので、電気を使いません。フルに巻ききると10分くらい。10インチのレコードには1曲(約3分)しか入らないのですが、これを2枚かけられるぐらいのパワーです。蓄音機というとラッパがついているイメージがあると思いますが、1936年ごろに作られたポータブル型にはついていません。
ラッパの構造(スピーカー)を中に仕込み、ふたの開口部の角度も含めてラッパの役割を果たしています。演奏会ではよく「ボリュームはどこで調整するんですか?」と聞かれますが、そういう構造はありません。曲の途中で音量を変えることはできませんが、針の太さで音量は変えられるので、太い針を使えば帝国ホテルの大広間でもマイクなしで全体に聞こえるぐらいの音量を出せます。
崎谷:佐藤さんご自身はいつから蓄音機にハマっているんですか?

佐藤:16~18年前くらいに、有楽町の素敵なカメラ屋さんのご主人が蓄音機にハマっていて、出入りするお客さんに聴かせてくれていたんです、強制的に(笑)。聴いたら、ものすごく、あふれるような生々しい音で。それまでにもオーディオに凝ったりはしていたんですが、それとは全然違う音で、なんだこれは!?と思ったんです。
自分の好きな音源のレコードを買っていってはそこのお店で聴かせてもらっていたのですが、そのうち自分でも欲しくなって蓄音機を1台買いました。そこからどんどんハマり、レコードも蓄音機も少しずつ増えていった感じです。蓄音機も楽器のように個体差・性格があって、クラシックに向くものがあれば、ジャズだといい音がするものもあるんですよ。
崎谷:蓄音機で聴く音はボリューム感、迫力が全然違って、音に包まれている感じです。音に集中できるので、視覚をすべてさえぎって、時間の観念もなく、音と自分だけという世界を演出できるのがすごいなと思いました。
佐藤:蓄音機のよさを言葉で表現するのって難しいんです。いい音がするから聞いてくれって言ってもなかなか伝わりづらいんですね。なら、どこにでも持って行って聴いていただきましょうということで演奏活動が始まったんです。

「シブヤ大学」「東京にしがわ大学」でのきっかけづくり
崎谷:NPO法人シブヤ大学授業コーディネーターもされています。2006年の開校当時、最先端ですごく話題になりましたが、佐藤さんはどういうかたちで関わり始めたんですか?
佐藤:じつは「押忍!手芸部」という男子の手芸団体に所属していて……ちなみに今日の帽子も私が編んだものです! そこの部長から、部員みんなで「シブヤ大学」の開校式に行こうと誘われたのがきっかけ。最初に出た授業も部長の授業でした。
おもしろかったので、毎月第三土曜日のスケジュールを開けて通うことにしたんです。1年半ぐらい通っているとスタッフともなかよくなって、蓄音機の話をしたところ、「おもしろそうだから授業にしましょう」と。
渋谷のライブハウスを教室にして音楽評論家の方とコラボしたりもしました。授業を企画することがどんどんおもしろくなっていき、いろいろ提案するうちに授業コーディネーターとしてやっていくことになりました。
崎谷:2008年には多摩エリアの姉妹校「東京にしがわ大学」もスタートしましたね。
佐藤:「シブヤ大学」は、街の人たちが先生になって、シブヤ全体をキャンバスとして街の魅力を発信していこうということで始まったプロジェクトです。市民大学の草分け的な存在なので、全国各地から地方でもやってみたいという方がいらっしゃって、札幌から沖縄まで9つの姉妹校が生まれました。
そのなかで多摩エリアは、東京なのにちょっと田舎で自然豊かで暮らしやすいエリア。この30市町村がいっしょになって何かできないかということで生まれたのが「東京にしがわ大学」です。
崎谷:30市町村全部! 難しいなか、大きく広げてやっていらっしゃったなんてすごいですね。
佐藤:大きく広げても、スタッフは全員ボランティア。仕事をしながらの活動で、自分たちでくまなく30市町村をコーディネートするのは難しく、オープンキャンパスとして30市町村に開き、参加者それぞれが30市町村に飛んで、見てきたものや感じたものを発表し合い、多摩の魅力を共有し合うというスタイルをとりました。
崎谷:参加者自体が先生の一部になり、30市町村に広げていくというかたちですね。
佐藤:誰かが先生になり、誰かが生徒になるわけですが、先生が一方的に伝えて教えるというよりも、参加者にとって学ぶことが多いのではないかと。いっしょにその場を共有し、ひとつのテーマで話すことで、新しいテーマや課題が生まれます。
私たちはきっかけを作ってちょっとだけ背中を押しますけど、あとはみなさんでやりたいことがあればご自身で深掘りしたり、興味を広げたり、その場の方たちと繋がったりする。そんなきっかけをつくるという機能だったのではないかと思っています。
自分がおもしろいと思うことを伝え、背中をそっと押していく
崎谷:佐藤さんとは西東京市の企業やお店を取材するお仕事で、カメラマンとライターとしてご一緒させていただきました。その頃から豊富な音楽知識を匂わせていらして(笑)。佐藤さんは趣味人なんですよね。
佐藤:おもしろいと思っていること、ハマっていることを人に話すことで、自分が違うところに連れて行ってもらえるんですよ。「それだったらこういう人に会ったほうがいいよ」とか。そういうところがおもしろいなと思っています。何かを始めるときの最初の一歩はもちろん自分の意思でいくけれど、そのきっかけを作ってくれる人が必ずいますよね。私も手芸部の部長との出会いがきっかけで、「シブヤ大学」に連れていってもらったわけですから。
崎谷:いい形で導かれていますよね。
佐藤:いい形でない場合もありますけどね。私の行動の原点になっているのは、「自分がおもしろいと思っているものは、他の誰かもおもしろいと思うはず。だったら自分だけではなく、それがいろいろな人に伝わるような提案をできたら」という思いです。
本にしたり、授業にするというかたちだけではなく、人と人、企業と人、行政と人……を繋げるきっかけを作れたら。人は何かをしたいというエネルギーが溜まったとき、ちょっとしたことが動くきっかけになる。「こういうのはどうでしょうね?」と、本人が気づかないくらいにやさしく背中を押して、きっかけを作りたいなと思っています。
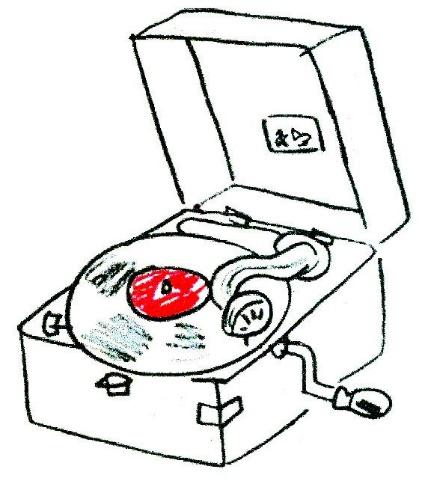
【佐藤隆俊さんProfile】
1953 年兵庫県宝塚市生まれ。幼少期を大阪府で、高校までを三重県で過ごす。映画カメラマンを志し、日本大学芸術学部映画学科で学ぶ。コマーシャル写真事務所を経て、1995年に佐藤写真工房を設立。カメラ・時計など金属の質感やメカニズムを切り撮る硬質な静物写真を中心に、広告・雑誌の撮影や旅の紀行文なども手掛ける。共著に『愛しのハッセルブラッド』『ライカのしくみ』(グリーンアロー出版社)、『ライカ症候群』(青林堂出版)など。
http://www.facebook.com/oyabinsato
